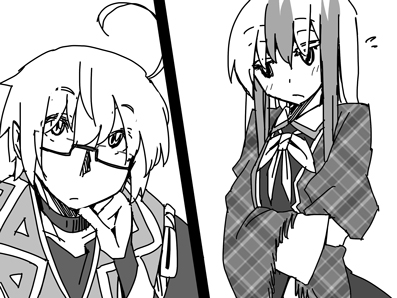後書き
■鈴月(「最果ての星」)
突然のはずれ合同のお誘いでしたが楽しく作業できました。はずれてありがとうございました。■りーくー(「けん・こう・こう・か!」)
皆さんほぼ初めましてだと思います。りーくーと申します。今回、Meteorideさんと鈴月さんと合同を作らせて頂きました! 感謝!
本も挿絵も初めてづくしなので、うまく出来たかどっきどきです。
どうかお正月のみかんのお供にでもお読みいただけたらと思います。
では他に言う事も無いのでこの辺で。読んで頂いた方々にとって、この本が「当たり」であった事を祈っております。
■メテオ(表紙・挿絵・編集)
「霖之助さんを嫁にもらう子は大変ね。霖之助さんのような甲斐性のない子を嫁にもらってくれる女性がいるのかしら」霊夢はお茶をすすりながら何でもないような顔をしてそう言った。僕がぎょっとしているとすかさず魔理沙が霊夢に続いた。
「ああまったくだ。香霖のようなずぼらで無愛想なやつを嫁にもらう女は大変だな。香霖が嫁にいけるか心配だぜ」
魔理沙は霊夢のようにさらりと言ったつもりだろうが、ところどころで閊(つか)えていて迫力に欠けていた。いやそもそも、僕はなぜ突然面と向かって悪口を言われているのだろうか。
「僕は男だから嫁じゃないだろう」
僕は霊夢をにらみつけた。しかし霊夢は僕の抗議を気に掛ける様子もなく
「いわばハズレね。霖之助さんを嫁にもらうなんてのは、ハズレくじだわ」
などとのたまった。ここまで悪し様に言われてさすがの僕もだまってはいられない。
「れ――」
「ああまったくだぜ」
ああ、なんてタイミングのいいことだ。まるで計ったかのように(いや、図っているのか)割り込んでくる。
「香霖を嫁にもらう女はきっとハズレさん――いや、ハズレちゃんだな。ハズレちゃんと呼ばれてしまうな」
なんだそれは。魔理沙はさも上手いこと言ってやったという顔をしているが、何も上手くない。そのままじゃないか。
「ええ、そうね。ハズレちゃんだわ」
僕が割り込む隙も与えず、霊夢が言う。霊夢はからっぽになった湯飲みをアンプ(注 音を増幅させるもの。空を飛ばないものだけを指す)の上に置くと、椅子に腰掛けたまま僕に正対した。
「だから、私がもらってあげるわ、霖之助さん。仕方ないわ、博麗は幻想郷の平穏と安寧のために身を捧げなくてはいけないもの。霖之助さんがどこぞの女のもとに嫁いで、幻想郷の平穏を乱すなんてことになったらただでさえ少ないお賽銭が雀の涙ほどもなくなってしまうわ」
霊夢は一息でそう言った。彼女にしては珍しく落ち着かない様子だ。いやまて、彼女は何を言った?
「霊夢、君ね。僕が嫁に行くことで幻想郷が、いやそもそも僕は男だから嫁じゃないと――」
言ってるだろう。とは続けられなかった。死角から何かが壊れるようなけたたましい音が聞こえたのだ。慌ててそちらを振り向くと、そこには木っ端微塵になった壺が、いや壺だったものがあった。いやもう無いのか。
「くっくっく……面白いことを言うじゃないか霊夢。いやいや、香霖が嫁ぐことで幻想郷の平穏が乱れると言うのなら、なに、わざわざ博麗の手を煩わせることはないさ。私が香霖をもらってやるよ。ああ、もちろんハズレちゃんと呼ばれようと私は気にしない。もともと、真っ当に人が生きる道からはハズレてるつもりだからな!」
口喧嘩をはじめるのは結構だがね、君らはどうせ口喧嘩で収まらないんだから店の外でやってくれないか。あと魔理沙、今し方破壊した壺はしっかり付けておくからな。
「安心しろ香霖。結婚したら付けは帳消しだぜ」
「あら魔理沙。そんな狭量で霖之助さんを受け入れられるのかしら。それとも、そんなにこだわって、もしかしてあんた…………霖之助さんのこと好きなの?」
霊夢の口の端がニヤリとつり上がる。一方の魔理沙はかあっと赤面すると、それをごまかすように大きく手をふるった。手をふるって別の壺を床に落として壊した。
「は、はん! そんなわけないだろ!? この甲斐性なしを好きになるって? 私はあくまでみんなのためにハズレくじを引いてやろうってことさ。だいたい、そんなこと言いだす霊夢こそ、香霖のことが好きなんじゃないのか!?」
「ふふ、面白いことを言うわね、魔理沙」
霊夢は余裕綽々と言った様子で、急須から本日三杯目のお茶を注ぐ。お茶を湯飲みになみなみ注ぐと、それを口に付けることもなく魔理沙をきっ、とにらむ。
「さっきも言ったでしょう? あくまで幻想郷のためよ。幻想郷を守るのは博麗の勤め。そして今の博麗は私よ。簡単な三段論法でしょう?」
いいや、そもそも僕が嫁にいったら幻想郷が荒れるという前提条件が狂っている、成り立たない三段論法だよ。とは思えど、あまりに下らない彼女たちのやりとりに、先ほどの罵詈雑言で芽生えた僕の怒りはすっかり収まってしまっていた。わざわざ口を挟んで火種をもらうこともないので、僕はさっさと読書に戻ろうと決めた。だが、唐突に現れた彼女はそれを許さなかった。
「ではどうだ? 実際にくじを引くというのは」
「慧音じゃないか」
「突然現れてなに言ってるのよ、あんた」
「おやおや、そんなことを言っていいのか? 素直になれない少女たちの意を汲んで、それとなく決着をうながしてやろうとしているというのに」
「誰が素直になれないんだ、誰が」
「言わずもがな」
にこにこと笑みを浮かべながら割って入ってきた人物は、慧音であった。買い物袋を下げているところを見ると、本来は真っ当なお客様たる用件であるようだ。
「何が入り用だい。チョークかな」
「まあまあ、そう事を急かして私を退場させようとするな。このままガヤガヤと騒がれるのも不本意だろう。なあ、店主殿?」
わざとらしい言い方をする。彼女が僕のことを「店主殿」だとか「香霖堂さん」だとか呼ぶときは、往々にして僕をからかおうと意地の悪いことを考えているときだ。しかし、このまま店内で喧々囂々やられるて困るというのは的を射たことであるので、ここは彼女の提案にのってやることにしよう。女性の我儘を受け入れてやるのもまた、良い男の条件というものだ。
「それで、くじを引くというのは?」
「そのままの意味さ。実際にくじを作って、それでハズレを引いた方が霖之助をもらえばいい」
「ふーん。ま、私はそれで良いわよ。まさにハズレってことね」
「ああ、私もそれで良いぜ。運命ってやつをこの手でたぐり寄せてやる」
いやまて、君らはそれで良いかもしれないが。
「僕は君らに貰われることを一切了承していない」
「女性の我儘を受け入れてやるのが、男ってもんだろう」
「む……」
「良いから早くくじを作れ。ほら、この竹籤(たけひご)で良いだろう。その先に印をつけて、それをアタリとすればいい」
そこまで言うなら君が作れよ。
「それじゃあ彼女たちが納得しないだろう。霖之助を取り合っているというのだから、霖之助がくじをつくるというのが筋だ」
そういうものだろうか。納得はしなかったが、抗議して彼女につくらせるよりも、のってしまったほうが色々と早く済みそうだ。そう判断して、竹籤を手に取る。ああ、まてよ。そうだ、何も「アタリ」と「ハズレ」の二本だけである必要はなかろう。何本もの竹籤の中から自分の手で運命をつかんでこそ僕の妻に相応しい。
「ほら、できたよ。さあ引くといい」
僕は十二本ほどの竹籤を左手に握って魔理沙と霊夢につきだした。
「……香霖、なんだこれは」
「くじだよ。話を聞いていなかったのか」
「なんで十二本もあるのかしら。アタリとハズレの二本で十分でしょ」
「そんな安い男じゃないよ僕は。十二本ですら少ないくらいだ。さあ早く引きなさい」
僕がうながすと、霊夢は不服そうな顔をしながらも迷いなくくじに手を伸ばした。魔理沙は霊夢とは対照的に、おそるおそるといった様子で左手を伸ばしてくる。
「ハズレを引いたものが霖之助をもらう。ハズレは印がついていない竹籤……それでいいな? 霖之助」
そうだとも。それがどうかしたのかい。
「いいや。ただの確認だ」
「ところでなぜ君もくじを引こうとしているんだ?」
「いいじゃないか、十二本もあるんだぞ。けちけちするな」
彼女の言い分は腑に落ちなかったが、なに、あと何人くじを引こうと問題ない。いや、あと九人引いたのなら僕が困ることになるか。
「良いか? せーので引くぞ」
魔理沙は親の敵でも見るような形相で手元の竹籤をにらんでいる。
「魔理沙、いくらにらんでも結果は同じよ」
「うるさい!」
「では、いくぞ」
三人が一斉に息を吸う。
「せーの!」
僕の拳から三本の竹籤が抜けていく。しかしそれらのどれにも印はついているのだ。すべてアタリ。彼女らからすればすべてハズレだ。
「ハズレだ!」
魔理沙が今にも泣きそうな声を上げた。彼女はハズレと言ったが、印が付いている。アタリだ。次に魔理沙は大げさに振り返ると、霊夢の手にある竹籤に目をこらす。
「…………アタリだわ」
もちろん霊夢の竹籤にだって印はついている。
「なに言ってるんだ。印がついているんだからハズレだろ」
「あんたこそ何言ってるのよ。印がついていないのがハズレ、でしょうが」
霊夢はあからさまに不機嫌な様子でその竹籤をしばらく見つめていた。魔理沙は未だに混乱している様で
「ん……? 印がついているからアタリか……いや、でもこれじゃ香霖を嫁にとれないってことだろ……? じゃあハズレじゃないか……?」
などとぶつくさ独りごちている。そんな魔理沙を横目でちらりとうかがうと霊夢はその竹籤をくず入れへと投げ捨てた。
「霖之助さんを嫁にとれないのがハズレって、あんたやっぱり霖之助さんのこと好きなんじゃない」
「なっ……! だだだ、誰が香霖なんか……!」
顔を真っ赤に染めてあわてる魔理沙を尻目に、霊夢は次に慧音のもつ竹籤へと目を向けた。無駄だよ。全て印がついているのだから。さあ、これで万事収めたりだ。読書に戻ろうか。
「ふふん。残念だったな霊夢」
「あ……」
間の抜けた声を出したのは霊夢ではない。魔理沙でもない(魔理沙は絶句していたのだ)。ほかでもない僕だ。彼女がもつ竹籤にはあるべき赤い印がなかった。
「そんな馬鹿な!」
僕は思わず声を荒げた。
「そ、そうだ! きっと印のほうを握っているんだろ!?」
魔理沙が慧音の右手に食いつく。魔理沙は慧音の持っていた竹籤を取り上げると、先ほどとは反対側の端を上にして高く掲げた。
「ついてないわ……ハズレよ……」
魔理沙とは正反対に、霊夢が消え入りそうなか細い声で囁いた。
「くくっ」
慧音が肩をすくめて笑みを浮かべた。
「よし決着がついた。では霖之助は私のものだ」
慧音は流れるように自然な動作で僕の背後に回ると、そっと腕を回した。そのあと慧音がどんな表情をしたか僕がうかがい知ることはできなかったが、霊夢と魔理沙が慧音の顔を見て、何かを感じたのは明らかで、二人ともなにも言い残すことなく、敗走するように香霖堂から去っていった。
「…………君、能力を使っただろう」
背中に慧音の重さと暑苦しさを感じながら僕はなんとか吐きだした。
「なんのことだ?」
「能力を使って、君の引いた竹籤に、僕が印をつけたという歴史を食ったんだ」
「それじゃあ五十点だな」
慧音がようやく僕から離れる。思わず肩を回し、首をならしていると、慧音は不愉快だとばかりに表情を曇らせた。
「……失礼」
「お前というやつは……」
言い訳の余地もない。彼女が退いてすぐに体をほぐしたんじゃ、重いと言っているようなものだ。このままでは立場がないので、話題を戻すことにした。
「それで? 能力を使ってないとでも」
「いいや、確かに使った。だが逆だ。お前が印をつけたことを食ったのではなく、印が書かれたことを食ったんだ。だが問題はそこじゃないだろう」
慧音が不敵に笑う。僕は思わずぎくりとした。
「いったいどうして店主殿は私が能力を使ったことがわかったんだろうか」
体裁こそ疑問の形式だが、その実まるで疑問ではない。その証拠に、彼女は僕を「店主殿」と呼んだ。
「勘さ」
言って即座に後悔した。
「いいや違う。お前は全ての竹籤に印をつけたのさ。だから私の竹籤に印がついていないのも見て、そんな馬鹿な、と言ったんだろ?」
慧音は引き出しに手を掛けると、その中から僕が仕舞ったばかりの竹籤を取り出し、これ見よがしに机の上に転がした。失態だ。失策だ。彼女は不正をそこそこ嫌う。それ以上に、僕をからかうことを楽しむ傾向にある(実に不愉快なことに)。彼女はこれを霊夢と魔理沙に告げて彼女たちから報復を受ける僕をせせら笑うのだ。
「いくらなんでもそこまで性悪じゃないぞ私は……」
慧音が溜息をついた。
「いいや、違う」
「意地が悪いな霖之助は」
「彼女たちは口ではハズレと言いながら、アタリを求めていたのは火を見るより明らかだった。つまりアタリこそがハズレだったんだよ。そしてどうだ、彼女たちは実際にハズレを引いたんだ。僕は彼女たちを思って全てに印を付けたのさ。彼女たちを思うが故の行為を、君が無碍にするとは到底思えないね」
「…………無理があるだろう、その理屈は」
「いいや、これが正解さ。仮に一本だけ印をつけないでおけば、彼女たちの仲を裂くことになりかねない。逆に全てに印を付けなければ一体これはなんだと責め立ててきて場は収まらないだろう。これが最善だったのさ」
「だが私がハズレを引いてしまったぞ」
「そもそも君がくじを引くことは想定外だ」
僕を見下ろす強い視線を、逸らさずに見つめ返す。しばらくの沈黙ののちに、慧音は呆れたように息を吐いた。
「まるで子どもだなお前は。昔からかわらん」
「君こそ意地の悪いところがかわらない」
「それはお前にだけだよ」
それまでまっすぐに僕に向かっていた視線がわずかに逸れる。
彼女の頬がわずかに紅潮するのも見逃さなかった。
僕は一瞬言葉に詰まる。
「……それじゃあまるで、好きな女の子にいじわるしたがる男の子じゃないか」
僕の言葉に慧音は面食らって、目を見開いた。
してやったり。そんな感情が僕の顔に出ていたのか、慧音は少し不機嫌そうに頭をかいた。
「ふん。彼らほど単純じゃあない」
「そいつは失敬」
僕がにやりと笑う。
慧音は観念したように大きく溜息をつくと、買い物袋を僕に突き出すように持ちあげて言う。
「じゃあ香霖堂さん、いつものやつをくださいな」
さあ、ここからは仕事だ。
今日はあまり手に入らない蛍光色のチョークを仕入れているのだ。
それを見た時の彼女の反応が楽しみである。
僕は開かないまま手に持っていた本を机に置くと、椅子から立ち上がった。
「かしこまりました、お客様」
(平成二十四年十二月二十六日 定時上がりした後で)